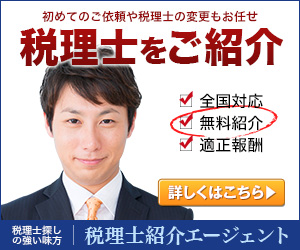「会社員だから確定申告は不要」と思っていませんか?
会社員として働いていると、通常は勤務先が年末調整を行ってくれるため、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、会社員でも確定申告をすべきケースがあります。

医療費が多くかかった人、ワンストップ特例制度を使用せずにふるさと納税をした人、住宅ローンを組みはじめた人など、確定申告をしないと損をすることも少なくありません。
しかし、
「確定申告って難しそう…」
「やり方が分からず放置してしまいそう…」
「知らないことで損をしていないか不安…」
といった悩みを抱えている方々も多いのではないでしょうか。
本記事では、会社員が確定申告すべき具体的なケースとその際の注意点について、私の2024年(令和6年)分の確定申告の経験を交えて、分かりやすく解説します。これらにより、あなたが確定申告すべきかどうかが分かり、正しく申告して節税や還付を受けることが可能になります。
会社員が確定申告を行う5つのケース

会社員でも確定申告が必要になるケースは主に以下の通りです。
- ①医療費が年間10万円以上かかった場合
- ②ふるさと納税をワンストップ特例なしで申告する場合
- ③副業収入が年間20万円を超えた場合
- ④住宅ローン控除の初年度
- ⑤年末調整で控除を受け忘れた場合
これらについて、
- ③は自主的に取り組んでいるため、確定申告に関する一定の知識はお持ちの場合が多い
- ④は住宅ローンを貸出した金融機関等から丁寧に教えてくれるケースが多い
- ⑤は会社加入の保険については会社で自動的に反映されるケースが多い上、任意の生命保険等はハガキ等で控除証明書が来るため、漏らすケースは少ない
ことから、本記事では、私の2024年(令和6年)分の確定申告の事例を交えて、①と②について重点的に紹介いたします。
医療費控除を受けられる場合
年間の医療費(自己負担分)が10万円以上(または所得の5%)を超えた場合、確定申告をすれば医療費控除を受けることができます。
例えば、家族全員の病院代や薬代、通院にかかった交通費も対象です(詳しくは、国税庁のHPを参照願います)。医療費の領収書をきちんと保管し、合計額を計算して申告しましょう。
<ポイント>
- 保険適用の診療費が対象
- 一部の保険適用外の診療費や市販薬の購入費も対象
- 健康保険で補填された金額は控除対象外
- 通院時のタクシー代や電車代も含められる
ふるさと納税の控除を受ける場合
ふるさと納税を5自治体以上に寄付した場合、ワンストップ特例制度が使えません。この場合は確定申告が必須となります。また仮にワンストップ特例制度を申請しても、確定申告を行った場合、ワンストップ特例制度の申請は無効となってしまうので、確定申告は必要になります。
申告することで、所得税の還付と住民税の減額が受けられるので、手続きを忘れずに行いましょう。
<ポイント>
- 寄付金受領証明書を必ず保管
- 控除額は収入に応じた上限があるため、超過分は控除されない
- 会社の年末調整では対応不可
副業収入が年間20万円を超えた場合
副業(フリーランス、ブログ収益など)で年間20万円を超える収入がある場合、確定申告が必要になります。確定申告を怠ると、税務調査の対象になる可能性があり、延滞税や加算税を課されることもありますので、注意が必要です。
<ポイント>
- 経費計上を忘れずに(PC、通信費、書籍など)
- 雑所得 or 事業所得の区分を理解
- 住民税の申告も忘れずに
住宅ローン控除の適用
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、初年度のみ確定申告が必要です。
2年目以降は年末調整で適用できますが、1年目の申告を忘れると控除を受けられないため、初年度は必要です。
<ポイント>
- 住宅ローンの借入残高証明書が必要
- 登記簿謄本、売買契約書のコピーも準備
- 控除額は最大40万円(2024年時点。条件により異なる)
年末調整で控除を受け忘れた場合
年末調整で申請し忘れた控除(生命保険料控除、扶養控除など)がある場合、確定申告で取り戻すことが可能です。
<ポイント>
- 過去5年間まで遡って申告可能
- 保険会社から送られてくる証明書類を保管
- 会社に頼らず自分で申告が必要
確定申告の事例紹介

今回、私は2024年(令和6年)分において、医療費控除の確定申告を行いましたので、実際の手続きに関する事例を紹介致します。
私は、ふるさと納税を毎年行っていますが、これまでは5自治体以下でしたので、ワンストップ特例制度を使用していました。
今回、2024年(令和6年)分においては、子供の歯科矯正費(保険適用外のため全額自己負担)が発生し、年間総額が10万円を超えましたので、確定申告をすることにしました。
2024年(令和6年)に行ったふるさと納税は5自治体以下でしたが、ふるさと納税前に確定申告をすることが決まりましたので、ワンストップ特例制度は申請せず、医療費控除に併せてふるさと納税も確定申告することになりました。
必要書類の事前準備

医療費控除及びふるさと納税の確定申告には、以下の書類が必要になります。
- 源泉徴収票(勤務先から発行)
- 医療費の領収書・明細書(医療費控除を受ける場合)
- 寄付金受領証明書(ふるさと納税の適用を受ける場合)
寄付金受領証明書は、インターネット上でふるさと納税を行った際、確定申告を行う旨を選択したため、後日、各自治体からハガキ等で届きました。
また、医療費については、日頃から領収書を保管しておいた他、健康保険組合から通知される「医療費のお知らせ」を電子データで受信しました。ただ、受信したデータは2023年12月から2024年11月までと期間が中途半端ですが、2024年分を申告する方法については、後述するマイナポータルでデータ反映が可能です。一方、歯科矯正費は保険適用外であるため、領収書のみでの対応になります。
マイナンバーカードとe-Taxを活用して確定申告

確定申告は税務署で手続きすることも可能ですが、マイナンバーカードとe-Taxを利用するとオンラインでスムーズに申告が出来ます。
マイナンバーカードとe-Taxを利用するメリットは以下の通りです。
- 24時間対応で好きな時間に申告できる(税務署へ行く手間が省ける)
- 還付金の振込が早い(紙申告より早く処理される)
- マイナポータルで、当該年分の医療費と寄付金(ふるさと納税)がデータで反映できる
基本的に国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にて質問事項に回答する形で進めていけば問題ありません。一方、手続きに時間がかかるため、作成途中の内容も保存できるようになっています。作成途中で各画面下部の「ここまでの入力内容を保存」ボタンと押下することにより、作成を中断しても次回作成時には続きから入力が可能です。作成を中断しなくてもこまめな保存をオススメします。
また、当該年分の医療費と寄付金(ふるさと納税)については、マイナンバーカードでマイナポータルにログインの上、「確定申告」を選択すると「確定申告の事前準備」画面に移り、各種控除証明書を取得することが出来ます。ここで、「医療費控除」や「寄付金控除(ふるさと納税)」を選択の上、連携(データの反映)が可能になります。
なお、医療費については、先述した健康保険組合からの「医療費のお知らせ」とは異なり、当該年度分(私の場合、2024年1月から2024年12月まで)が反映されます。また、本人分のみの反映になるため、家族分については代理人設定が必要です。代理人設定により家族分も含めた医療費が反映されます。
もちろん、全額自己負担した歯科矯正費については、e-Taxにて上述の自動反映された医療費とは別に、手入力する部分がありますので、領収書を見ながら入力します。
確定申告の期間

基本的に確定申告期間は、毎年2月中旬から3月中旬までとなります。
今回、私は、住宅ローン控除以来の約10年振りの確定申告であったため、1月下旬あたりから早めに準備を始めました。
なお、今回の医療費控除と寄付金控除(ふるさと納税)については還付金を受ける申請、つまり「還付申告」にあたるため、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出が可能です。
そのため、私は2月上旬に医療費のデータが反映された直後に、2024年分の確定申告(還付申告)を行いました。また、過去5年分の医療費を調査しましたところ、一昨年の2023年(令和5年)分の医療費も10万円超えしていたため、こちらも併せて確定申告しました。
まとめ「確定申告を活用し、賢く節税しよう!」

会社員でも確定申告をすれば、税金の還付を受けたり、余計な税負担を減らしたりすることが可能です。以下のポイントを押さえて、確定申告を行うことが大切です。
- 医療費控除やふるさと納税の還付を受ける
- 副業の収入を正しく申告し、経費計上を活用
- 住宅ローン控除や年末調整漏れを申告で補完
特に、「医療費が年間10万円以上かかった場合」は該当するケースが多い上、ふるさと納税を行っている場合は、医療費控除を行うことに併せて、ふるさと納税分も確定申告することになります。
以下、会社員向けの確定申告に向けた流れをまとめます。
1)日頃から、医療関係の領収書は保管する。(特に全額自己負担の医療費は保管必須)
※国税庁のHPを参照し、医療費控除に該当するか否かを確認
2)(医療費控除を申請するか否かが不明な場合)ふるさと納税時には、とりあえずワンストップ特例制度を申請(1月上旬まで)
3)(2月上旬から中旬頃に)マイナポータル反映された前年分の医療費と全額自己負担した医療費とを合算して10万円以上の場合、確定申告を実施。
※ふるさと納税でワンストップ特例制度を申請していた場合でも、確定申告をすれば、ワンストップ特例制度の申請が無効になり、確定申告の申請が適用される)
本記事を読んだ今が、確定申告の準備を始める絶好のタイミングです。今年こそ、確定申告を活用して賢く節税しましょう!